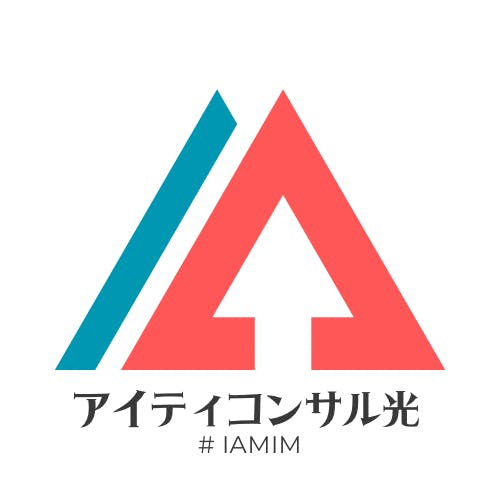患者さんは、あなたの「世界観」なんてどうでもいい。痛みが取れるなら、説明文はコピペで構わないと断言できる理由。

「私の院は、そんじょそこらの整骨院とは違うんです」 「このテンプレートの安っぽい表現は、私の高尚な治療哲学とは相容れない」 「私の患者さんは、もっと知的で、行間にあるニュアンスを求めているはずです」
かつて、コンサルティングの現場で、私は何度この言葉を聞いただろうか。 そして、正直に告白しよう。 かつての私自身も、深夜の鏡の前で、充血した目で同じセリフを吐いていた一人だ。
私たちは、自分の城である治療院を愛しすぎている。 自分が磨き上げてきた技術、こだわり抜いた内装、患者さんとの間に流れる独特の空気感。 それらはすべて、あなたの血と汗の結晶であり、世界に二つとない「芸術作品」だ。

だからこそ、市販の「集客テンプレート」や、誰かが作った「反応の取れる文章の型」を提示されると、本能的な拒絶反応が出る。 まるで、自分が丹精込めて作った最高級の三ツ星フレンチを、コンビニのプラスチック容器に詰めろと言われたような屈辱を感じるのだ。
「こんな画一的な言葉では、私の想いは死んでしまう」 「私の独自性が、大衆迎合的なノイズに埋もれてしまう」
そうやって、あなたはまた、真っ白な画面に向かい、自分だけの「完璧な言葉」を探す旅に出る。 深夜2時、3時……。 翌日の施術のパフォーマンスが落ちることを知りながら、それでも「納得のいく表現」を求めて、あなたの命とも言える時間を溶かし続ける。
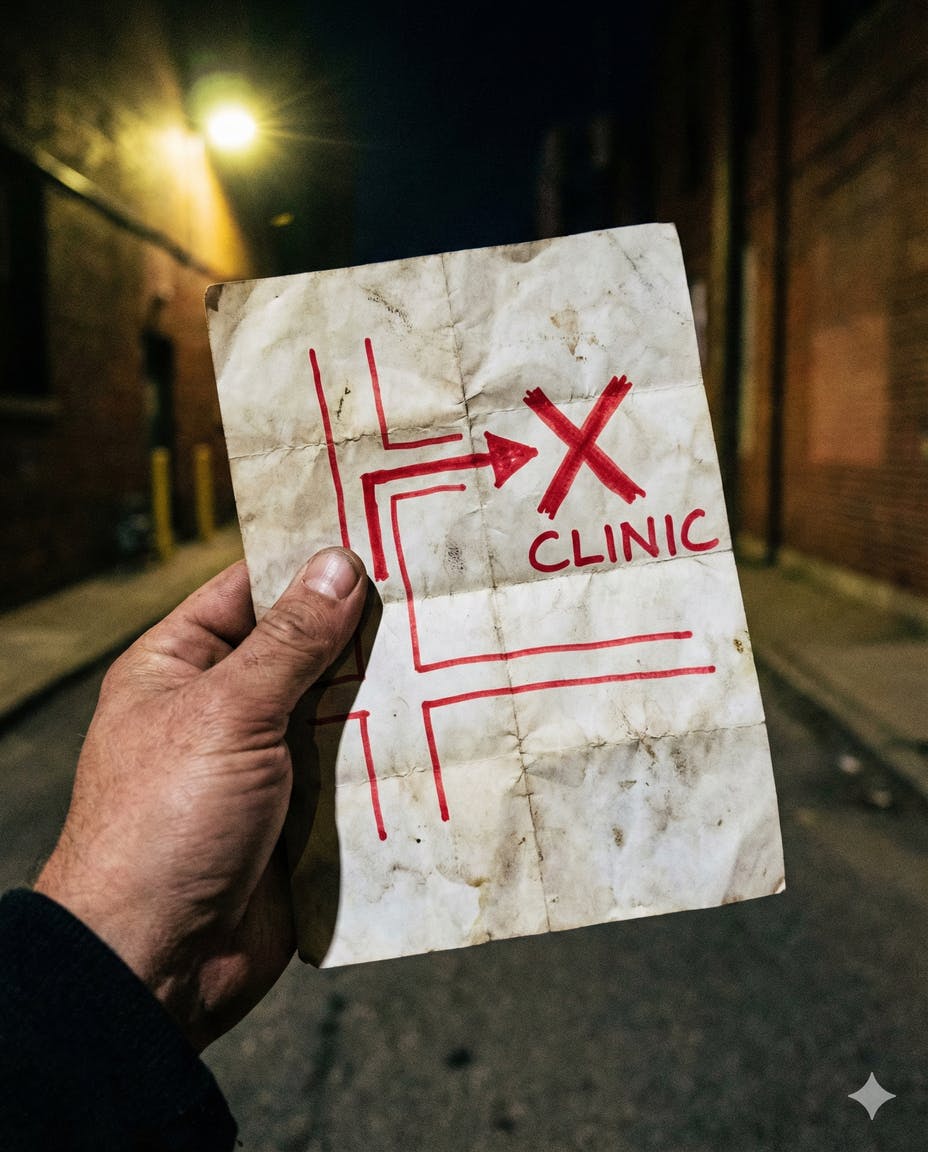
だが、ここで一度、冷水を浴びせるような残酷な質問をさせてほしい。
その「こだわり」は、あなたが明日倒れた時、家族の生活を守ってくれるだろうか? そして、その「こだわり」は、今まさに激痛に苦しむ患者さんを救ってくれるだろうか?
患者さんの視点に立ってみよう。 今まさに、ギックリ腰で脂汗を流し、這うようにしてスマホを操作している田中さん(仮名)を想像してほしい。
彼が、痛みに歪む顔で必死に探しているのは、あなたの高尚な「治療哲学」だろうか? あなたの院に流れる「独特のアンニュイな世界観」だろうか? あなたが徹夜で紡ぎ出した「文学的な表現」だろうか?
違う。絶対に違う。断じて違う。
彼が求めている情報は、極めてシンプルで、残酷なほど即物的だ。
「この痛みは取れるのか?」 「場所はどこだ?」 「今すぐ行けるか?」 「いくらだ?」
以上だ。
極限状態の彼らにとって、あなたの文章が、どこかの天才マーケッターが作った「型」のコピペであろうが、あなたが魂を削って書いたオリジナルの詩であろうが、そんなことはどうでもいいのだ。 「私の痛みを解決してくれる場所への地図」でありさえすれば、それが手書きの汚い地図でも、印刷されたGoogleマップでも、構わない。
むしろ、あなたが「独自性」を出そうとして、奇をてらった表現や難解な言い回しを使えば使うほど、痛みで思考力が落ちている患者さんにとっては「ノイズ」になる。 「結局、治るのか治らないのか分からない」とイラつかせ、無言で「戻るボタン」を押させてしまう。
それは、あなたの「こだわり」が、患者さんを救うどころか、「入口で門前払い」しているのと同じことだ。 これが、あなたの望んだ「独自性」の末路なのか?
テンプレートを使うことは、あなたの個性を殺すことではない。 むしろ、「あなたの個性を、最も安全に、最短距離で患者さんに届けるための『頑丈なトラック』を用意すること」だ。
トラックの荷台(テンプレート)が量産品であっても、その中に積まれている荷物(あなたの技術と人柄)が本物であれば、価値は1ミリも変わらない。 むしろ、独自の手作りリヤカーで運ぼうとして、途中で力尽きて倒れるより、量産品のトラックで確実に、迅速に患者さんの元へ届ける方が、よっぽど「誠実」な医療従事者の態度ではないだろうか。
そして何より、私があなたに「型」を使ってほしい最大の理由は、集客のためではない。 あなたの「命」を守るためだ。

文章作成ごときに、あなたの貴重なエネルギーを使わないでほしい。 「何をどう書こうか」と悩む時間は、あなたの睡眠時間を削り、精神をすり減らす。
私たちが倒れた瞬間、収入はゼロになる。 完全に、即座に、ゼロだ。 そんな薄氷の上を歩いている私たちが、一円にもならない「推敲」で疲弊し、そのせいで病に倒れたとしたら……それはもはや事故ではない。 プロとしての「過失」だ。
型を使えば、3時間かかっていた作業が15分で終わる。 その浮いた2時間45分で、あなたは眠ることができる。 家族と笑い合うことができる。 明日の患者さんのために、鋭気を養うことができる。
その「余白」こそが、あなたが治療家として長く生き続け、より多くの患者さんを救うための生命線になる。
プライドを捨てよう。 「私の院は特別だ」という呪いを解こう。
入り口(広告・文章)は、どこにでもある「自動ドア」でいいのだ。 何の変哲もない、スムーズに開く、ありふれた自動ドアだ。
患者さんがそのドアを通り抜け、あなたの施術室に入り、あなたの手に触れた瞬間。 その時初めて、あなたの「圧倒的な独自性」を見せつければいい。 「ああ、来てよかった。ここは他とは違う」と、肌で感じてもらえばいい。
インターネット上の文章だけで、あなたのすべてをわかってもらおうなんて、図々しいにも程がある。 本物の勝負は、会ってからだ。
さあ、肩の力を抜いて。 ありふれた、つまらない、しかし驚くほど機能する「型」を手に取ろう。
それは、あなたがプロフェッショナルとして、自分と家族、そして未来の患者さんを守るための、最強の盾となるはずだ。