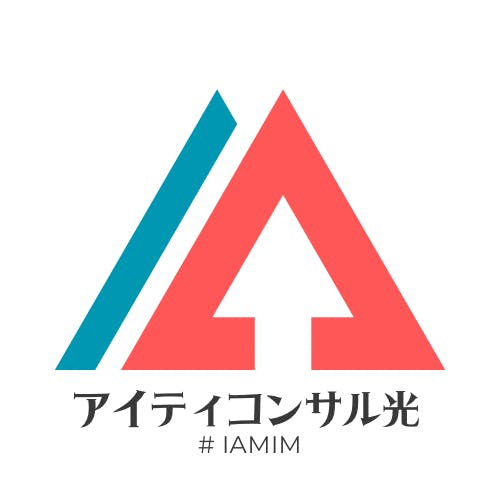「楽をして稼ぐこと」への罪悪感を今すぐ捨てなさい。さもなくば、あなたは一生、"労働"という名の檻から出られない。

施術が終わった後の、あの独特の匂いが好きだった。
消毒用エタノールの冷たい香りと、患者さんの身体から立ち昇る熱気。 そして、自分のかいた汗の匂いが混じり合った、治療院特有の空気。
夜の11時。 誰もいなくなった院内で、最後のカルテを書き終え、ふと自分の掌を見つめる瞬間。
「今日も、いい仕事をした」
身体は鉛のように重い。腰も悲鳴を上げている。 けれど、その疲労感こそが、私にとっての「勲章」だった。
額に汗して、自分の身を削って、その対価としてお金をいただく。 これこそが「誠実」であり、治療家としての「正義」だと信じて疑わなかった。
逆に、自分が動かずにお金が入ってくる仕組みなど、「悪」だと思っていた。
「寝ている間に稼ぐ? 自動化? ふざけるな」
そんなものは、詐欺師のやることだ。 汗もかかずに得た金なんて「あぶく銭」だ。 そこには魂がこもっていない。 そんな金で家族を養うなんて、職人のプライドが許さない。

そうやって、私は効率化を提案してくる業者を門前払いし、 「手作業」と「長時間労働」という名の宗教に、深く、深くのめり込んでいった。
あの日、私の身体が強制終了するまでは。
警告はあったはずだ。 時折走る背中の痛み。朝、起き上がる時の眩暈。
でも、「気合が足りないだけだ」と無視した。 自分が倒れるなんて想像もしなかった。 私は人を治す側で、治される側になるはずがないという、根拠のない万能感があったからだ。
そして、その日は突然やってきた。
朝、ベッドから一歩も動けない。 天井がぐるぐると回り、吐き気が止まらない。 救急車を呼ぼうとスマホに手を伸ばすが、指に力が入らない。
その時、私の脳内を駆け巡ったのは、 「身体が痛い」という恐怖ではない。
「今日の予約、どうしよう」 「来週の支払い、間に合うか?」 「俺が動けなかったら、今月の売上はゼロだ」
そんな、あまりにも即物的で、冷ややかな絶望だった。
ベッドの上で身動き一つ取れない私は、ただの「無力な肉塊」だった。 昨日まで誇りに思っていた「汗水垂らして働くこと」への執着が、今、私の首を真綿のように締め付けている。

私が動かなければ、1円も入らない。 それが、私が崇拝していた「清貧の美学」の正体だった。
皮肉な話だ。 私は「誠実さ」を追求しているつもりで、実はとんでもない「不誠実」を犯していたのだ。
自分というエンジンが一つ壊れたら、即座に沈没する泥船に、 何も知らない家族やスタッフを乗せていたのだから。
高熱にうなされながら、私は天井のシミを見つめて考えた。
もし、あの時。 「楽をして稼ぐなんて汚い」という偏見を捨てていたら?
私がこうして高熱で寝込んでいる間も、 システムが自動で予約を受け付け、患者さんに安心するようなメッセージを送り、 私の代わりにセルフケア動画が患者さんの痛みを和らげ、 物販の注文が自動で処理され、売上が立っていたら?
それは「汚い金」だろうか? 「あぶく銭」だろうか?
いいや。違う。
それは、私が倒れた時に、家族の生活を守るための**「命綱」だ。 患者さんを路頭に迷わせないための「責任」**だ。
私が毛嫌いしていた「自動化」や「仕組み」は、 サボるための道具なんかじゃなかった。
自分という人間が、いつか必ず老いて、弱って、動けなくなる生き物であることを認めた上で、 それでも周りを守り抜こうとする**「優しさ」の形**だったのだ。
先生、あなたに問いたい。
あなたは今、その「手」だけで戦っていることに酔いしれていないだろうか? 「忙しい」という言葉を、心の安定剤にしていないだろうか?
「楽をすること」への罪悪感を捨てなさい。 それは怠惰ではない。進化だ。
あなたが現場を離れても、あなたの分身が価値を提供し続ける。 その仕組みを作ることは、手技を磨くことと同じくらい、いや、それ以上に尊い「仕事」なのだ。
汗をかいて稼ぐお金は尊い。 だが、汗をかかずに稼ぐお金は、あなたの大切な人を守る「盾」になる。
どちらか一つを選ぶ必要はない。 両方持っていなければ、本当のプロとは言えないのだ。

私は、あの絶望のベッドの上で、プライドという名の重い鎧を脱ぎ捨てた。 そして、泥臭い職人であることをやめ、冷徹な守護者としての視点を持つことを誓った。
今、私の院では、私がハサミを入れることなく、予約が入り、ビジネスが回っている。
そのおかげで、私は空いた時間で体調を整え、家族と笑い、 そして万全の状態で、目の前の患者さんに「最高の施術」を提供できている。
施術で最高の汗をかくために、経営では汗をかかない。 これが、私がたどり着いた答えだ。
これが「悪」だと言うなら、私は喜んで悪魔になろう。 清廉潔白な貧乏人として家族を道連れにするより、泥にまみれても生き残る道を選ぶ。
あなたは、どうする? まだ、その「労働という名の檻」の中に留まり続けるか?
鍵はかかっていない。 ただ、あなたが「出る」と決めるだけでいい。
その一歩を踏み出すのが怖いなら、鏡を見て問いかけてみてほしい。
「もし明日、この手が動かなくなったら、誰が家族のご飯を食べさせるのか?」
さあ、顔を上げて。 檻の外の世界は、あなたが思っているよりもずっと、広くて、温かい。